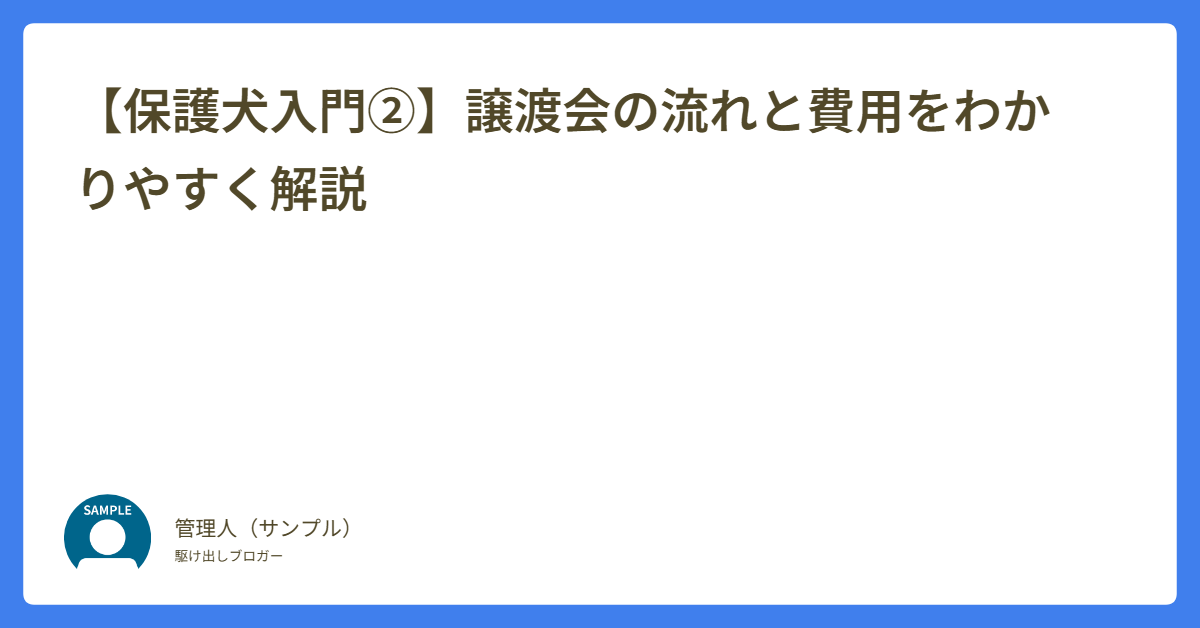【保護犬入門】現状から譲渡会の流れまで完全ガイド
「保護犬を迎えたいけど、どうすればいいの?」
「譲渡会ってどんな流れなの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では 保護犬の現状 から 譲渡会の流れ までをわかりやすく紹介します。
犬を飼ってみたいと思っている方やご家族は、
ぜひ一度、保護犬という選択肢 について知ってみてください。
保護犬の現状
保護犬とは
保健所、動物愛護センター、民間の保護団体などに保護されている犬の総称です。年齢や犬種はさまざまで、子犬から老犬まで、純血種から雑種まで幅広く存在します
保護犬になるいきさつ
- 飼い主による飼育放棄や虐待
- 飼い主の高齢化、病気、離婚、引越しなどの事情
- 迷子になった犬や野良犬
- 悪質なブリーダーによる遺棄や繁殖引退犬
- 多頭飼育崩壊
- 災害や事故などの不測の事態
殺処分数は減少傾向
かつて日本では、年間数万頭もの犬が殺処分されていました。
しかし、ここ10年で大きく改善しています。
📊 概要:2023年度の犬猫殺処分数(環境省発表)
| 区分 | 殺処分数 | 引き取り数 | 備考 |
| 犬 | 2,118頭 | 約19,352頭 | 約11%が殺処分 |
| 猫 | 6,899頭 | 約25,224頭 | 約27%が殺処分 |
| 合計 | 9,017頭 | 約44,576頭 | 初の1万頭以下 |
※出典:環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(令和5年度)
自治体やボランティア団体の努力、そして「保護犬を迎える」という選択肢が広がったことが大きな要因です。
保護団体の活動が支えている
保護犬の多くは、動物愛護センターから引き出されたのち、NPOやボランティア団体によって保護・ケアされています。
病気治療やトレーニングを経て、譲渡会などで新しい家族を探します。
ただし、団体によっては医療費・保護場所・人手の不足が深刻です。
活動資金は寄付やフリーマーケット、クラウドファンディングに頼ることが多いのが現状です。
保護犬を取り巻く課題
- 成犬や老犬の譲渡が進みにくい
- 「子犬」を求める風潮が根強い
- 一部の悪質ブリーダー・繁殖業者による「繁殖犬問題」
- 保護施設の運営資金不足
特に繁殖引退犬(ペットショップに子犬を供給していた親犬)の存在が注目されるようになっています。
保護犬を支援する方法
- 里親になる
- 一時預かりボランティア
- 寄付や譲渡会の手伝いなどの支援活動
里親になるためには
保護団体や譲渡会を探す
まずは、保護犬を扱う動物愛護団体や自治体のセンターを探します。
SNSや譲渡会情報サイトからも見つけられます。
気になる団体があれば、活動内容や譲渡条件をしっかり確認しておきましょう。
譲渡会の流れをわかりやすく解説
「保護犬を迎えたいけど、譲渡会ってどういう流れなの?」
そんな方に向けて、一般的な譲渡会の流れを紹介します。
① 事前に情報をチェック
まずは、開催団体のホームページやSNSで日時・場所を確認します。
多くの団体では、事前予約制になっている場合があります。
気になる犬がいる場合は、あらかじめエントリーしておくとスムーズです。
② 会場での受付
当日は受付で、来場目的(見学・里親希望など)を伝えます。
アンケート用紙を記入する場合もあります。
家族全員での参加が求められることも多いです。
③ 犬たちとのふれあい
会場では、ボランティアさんの見守りのもとで犬と触れ合えます。
緊張している子も多いので、静かに優しく接することがポイント。
その子の性格や過去の経緯をスタッフさんから聞いてみましょう。
④ 里親希望の申し込み
気になる子が見つかったら、スタッフに相談します。
その場で「里親希望の申込書」を書く場合もあれば、
後日改めて連絡を取る流れの場合もあります。
⑤ 面談・トライアル(お試し期間)
譲渡がすぐに決まるわけではありません。
家庭環境や飼育環境を確認するための面談が行われ、
条件が合えばトライアル期間(1~2週間程度)がスタートします。
⑥ 正式譲渡
トライアルが無事に終わり、
「この子とずっと暮らしたい」となったら正式譲渡です。
譲渡契約書を交わし、医療費などの譲渡費用を支払います。
🐶まとめ
譲渡会は、犬と人が出会う大切な場。
焦らず、ゆっくり相性を見ながら進めることが大切です。
見学だけでも大歓迎な会も多いので、
まずは気軽に足を運んでみてはいかがでしょう。